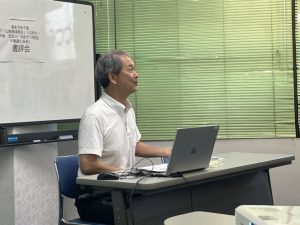公害地域再生をめぐる対話――清水万由子著『「公害地域再生」とは何か』書評会を開催(9/6)
9月6日(土)、あおぞら財団で清水万由子著『「公害地域再生」とは何か~大阪・西淀川「あおぞら財団」の軌跡と未来』をテーマに書評会を開催しました。著者の清水先生を囲み、研究者や実践者など多様な立場の方々が語り合う貴重な時間となりました。会場はあおぞらビル3Fグリーンルーム。参加者は現地17名(スタッフ・コメンテーター含む)、オンライン15名の計32名でした。
前半は3人のコメンテーターが登壇。除本理史氏(大阪公立大学)は川崎市や倉敷市水島地区の事例と比較しつつ、「公害経験の継承とまちづくりをどう結びつけるか」という論点を提示しました。茅野恒秀氏(法政大学)は「あおぞら財団の実践と人びとの経験を描き出した好著」と評価し、吉田忠彦氏(近畿大学)は「多様な人が乗り降りする“乗りもの”としてのあおぞら財団」という視点を示しました。これらに対して清水先生がリプライし、議論は深まっていきました。
後半のミニシンポには清水万由子先生、尼崎南部再生研究室(あまけん)の若狭健作氏、あおぞら財団の藤江徹氏も加わり、現場からの視点が議論に厚みを加えました。
参加者からは、
「各コメンテーターの組織・現場経験が反映され、議論に厚みがあった」
「都市の記憶を忘却せず掘り起こし続ける取り組みの熱量に感銘を受けた」
「財団を“舟”に見立て、誰が次世代の担い手になるのかをめぐる議論が印象的だった」
「公益財団という組織形態の意義と難しさについて考えさせられた」
といった声が聞かれました。
過去の経験を未来へどうつなぐか、地域再生の主体は誰か――笑いも交えながら、多面的で熱のこもった対話が続きました。最後は西淀川・公害と環境資料館(エコミューズ)の見学で締めくくられました。
今回の書評会を通して、あおぞら財団が果たす役割があらためて浮き彫りになったと感じました。公害地域再生をめぐる対話は、これからも続いていきます。
参考
・清水万由子著『「公害地域再生」とは何か――大阪・西淀川「あおぞら財団」の軌跡と未来』、藤原書店(2025)
・除本 理史・立見 淳哉 編著『「地域の価値」とは何か―理論・事例・政策』、中央経済社(2024)
・茅野 恒秀・青木 聡子/編 『地域社会はエネルギーとどう向き合ってきたのか』、新泉社(2023)
・吉田 忠彦 著『NPO支援組織の生成と発展 — アリスセンターによる市民活動支援の軌跡』、有斐閣(2024)