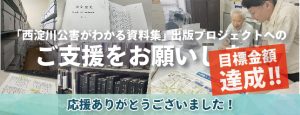2日間の動きをまとめて報告しましょう。
2月9日月曜日は、資料集編集委員会が開かれました。大阪公立大学の佐賀先生、岡山大学の松岡先生はオンラインでの参加。財団職員の鎗山さんから編集の進捗状況の報告がなされました。原稿もほぼ確定し(残るのは索引と奥付のみ)、基本的には順調に進行していることが紹介され、また、寄附金の募集も目標としていた金額を15万円以上も上回って達成いたしました。
ただ、思ってもみなかった問題が出版を担当していただいている阿吽社さんから提起されており、それは、資料の中に児童の作文、学校の先生の署名入りの研究報告など、どこから見ても著作権の所有権があることが明らかな資料が含まれていることに対する対応です。
編集委員会ではこの問題についての基本的な考え方が議論され、やはり、著作権者の了解を得ること、その権利を認めるために手を尽くさなければならないことが語り合われました。文化庁の裁定制度というものがあることも紹介され、それを利用した方がいいのではないかという意見が出されました。
さらに、次回は4月以降に本の出版と合わせて最後の委員会を開催し、みなさん、リアルに参加して出来上がった本を前にともに喜びたいものだと確認しました。また、わたくしの方から両先生に本を広めていただくように依頼し、快く受け入れられました。
会議終了後はさきほど述べた著作権者が不明の方に対する対応方法について、凡例に文章を掲載し、また、奥付けの部分にも同じく文章を掲載することを考えて、その原案を作りました。
翌日は、それを出版社である阿吽社さんの方と一緒に検討することを確認してこの日は終わりました。
以上が2月9日の出来事です。いっぱいありました。
ここまでで二日分の仕事をした気がしております。
2月10日。今日は阿吽社職員の松本さんとオンラインで話し合いを重ねて、昨日の検討に基づいて、凡例の文章を検討し、完成させました。それから、著作権所持の方に対する呼びかけを検討いたしました。
それで、こんど作られる本の中にはたくさんの人物が登場します。この人物について対応の仕方は少し考えておかなければならない、とういことになりました。どのような人物が登場するかといえば、一つは、今まで、語ってきた著作権を持っているがその方の所在がわからなくなっている方。二番目は住所、電話番号などプライバシーが不必要に表記されている人物。三番目は特定の人物に対する意図的な印象付けをするような文章の対象となっている人物。四番目は運動の担い手として、名前が登場する方。五番目は行政の担当者としての名前が登場する方などです。
これらの人々をどう扱うべき方ということについては、おそらく、従来あまり検討されたことのない課題に直面したものと考えざるを得ませんでした。結果として、文化庁の裁定制度を利用することを決定しましたので、その都合上、出版は3月末はちょっと困難であり、5月ごろかな、と、そのころになる可能性が大きいという意向に到達しました。
3月末発行を楽しみにしていた方には、もうしばらくお待ちいただきたいと思います。
2026.2.10 小田康徳
—————————
あおぞら財団付属 西淀川・公害と環境資料館(エコミューズ)では、西淀川公害がわかる資料集を作成しようと、ほぼ毎週、小田康徳館長が来館し、調査作業を進めています。そのようすを「エコミューズ館長日記」にてお届けします。
【お礼:目標達成】西淀川公害がわかる資料集 出版プロジェクト
2024年8月から呼びかけてまいりました「西淀川公害がわかる資料集 出版プロジェクト」への寄附募集ですが、おかげさまで、約315万円が集まり、目標としていた300万円を達成することができました。本当に多くの方々に支えていただき、スタッフ一同、心より感謝を申し上げます。いただいたご寄附は大切に使わせていただきます。
本プロジェクトはこれからも資料集の出版、普及など続いてまいりますので、どうぞ今後も引き続きご支援ご協力をいただけますと幸いです。
■寄附プロジェクトはこちら https://www.aozora.or.jp/ecomuse/contibution_doner
※資料集のウェブ版作成には、(独法)環境再生保全機構地球環境基金助成金を活用しています。
#おもろいわ西淀川
#にしよど
#魅力発信サポーター
#エコミューズ
#西淀川公害がわかる資料集