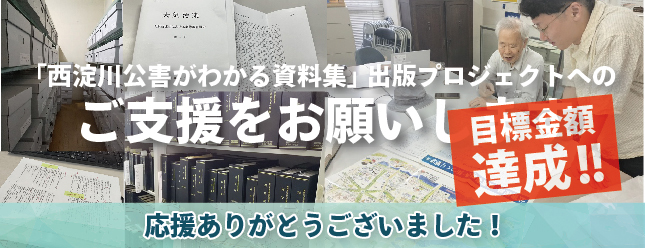2024年8月から呼びかけてまいりました「西淀川公害がわかる資料集 出版プロジェクト」への寄附募集ですが、おかげさまで、約315万円が集まり、目標としていた300万円を達成することができました。
本当に多くの方々に支えていただき、スタッフ一同、心より感謝を申し上げます。
いただいたご寄附は大切に使わせていただきます。
資料集は出版社が決まり、ただいま、初校を校正しているところです。
使用する資料の掲載許可の手続きなど、いくつか対応を要する事項があるのですが、順番に取り組んでいるところです。
2026年春ごろの発行をめざしています。
今回、みなさまからいただいた大きな支援を原動力にして早く資料集をお手元へ届けられるよう進めてまいります。
どうぞこれからも見守っていただけますと幸いです。
このたびは、誠にありがとうございました。
———————-
■「エコミューズ館長日記」
資料集出版までの過程を知っていただこうと、2024年8月から「エコミューズ館長日記」と題して、あおぞら財団サイトのブログに日記を掲載しています。
https://aozora.or.jp/archives/category/ecomuse/ecomusediary
■資料集の一部は、ウエブ版としてHPにも掲載しています。
https://www.aozora.or.jp/ecomuse/data
※ウェブ版資料集の作成には地球環境基金の助成金を使用しています
#西淀川公害
#西淀川・公害と環境資料館
#エコミューズ
#西淀川公害がわかる資料集
#おもろいわ西淀川
#にしよど
#魅力発信サポーター