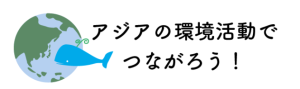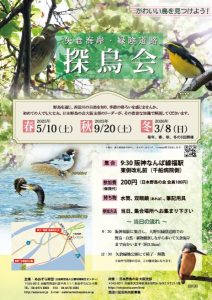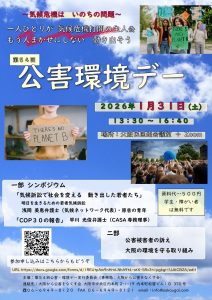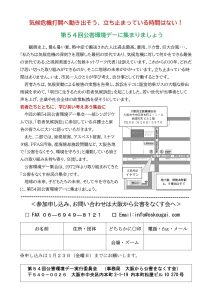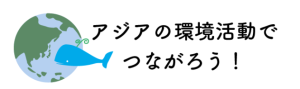11/13に日中環境問題サロン2025を開催しました。
グローバルな経済活動が展開される中で、今日の公害・環境問題は地域や国をこえた形で発生し、互いに影響しあっています。
中国の環境NGOおよび環境事業を取り組む団体のメンバーを招き、中国の最新の環境問題について報告いただき、日本の市民、専門家やNGO関係者、企業との意見交換を行う日中環境問題サロンを開催しました。今後の日中における公害・環境問題の解決に向けて、お互いに理解し、協働していくための意見交換をおこないました。
あおぞら財団事務局長藤江と中国訪問団リーダー李力氏の開会あいさつによって、日中環境問題サロン2025が始まりました。
「自然の美しさを享受し、エコ文明の実践者になろう」
最初の発表者は、黒竜江省八五三農場幼稚園・園長宋波氏です。
宋氏の幼稚園が、環境教育を充実に取り入れています。
・大自然を触れ合う:園児を林に連れ、自然に触れ合うゲームを通して、自らの肌で自然を感じさせます。
・植物を世話する:園内に植樹します。植物の水やりや葉の手入れは、園児がしてもらいます。園児が植物との「付き合い」によって、自然環境への関心が培うことが期待されます。
・ゴミ分別やアップサイクル:幼稚園からゴミ分別の習慣を身に付けることを目指します。また、ペットボトルなどの廃棄物をアップサイクルし、「水ロケット」を作ります。アップサイクルをゴミ問題の解決策の一つとして園児に知ってもらいます。
・ゼロウェスト:食べ物に常に感謝の意を込めて、完食するよう促します。給食の量を少なめにし、足りない子におかわりしてあげるの形で、完食の習慣を身に付けることを目指します。

発表している宋氏
「湿地の気候変動対応協働活動」
次の発表者は、合肥市善水環境保護発展センター(以下「善水」と呼ぶ)・執行主任張登高氏です。
張登高氏が所属する団体「善水」は、河川・湖の生態保護、コミュニティと湿地保全が共生できる方法を模索する環境保全団体です。気候変動や環境問題に対して、湿地のレジリエンス(復元力・耐久力)を高めることが、当団体の目指しです。
張登高氏の発表を通して、湿地保全という環境対策における積極的な市民参加の可能性が見られました。
コミュニティ、湿地管理部門、「善水」が協約を結び、環境の豊かな住みやすい地域を目標としてまちづくりを行います。有志の地域住民を「湿地ガイド」や「湿地保護隊」を育成する。一般市民が「湿地ガイド」の湿地解説を聞いたり、「湿地保護隊」の活動・調査報告を見たり、環境意識が向上されます。また、「湿地ガイド」や「湿地保護隊」が湿地管理部門から給料をもらって、持続可能な環境保全・環境教育の輪が広がることが期待されます。

発表している張登高氏
「医療廃棄物の科学的処理:環境と気候を守る重要な防衛線」
最後の発表者は、山西数酷大数据科技有限公司・会長張志栄氏です。
張志栄氏が、現在山西省太原市の医学連合会の会員であり、高齢者介護と医療廃棄物の適正処理について研究されています。
張志栄氏の発表を通して、医療廃棄物の処理が不適切であれば、衛生上の問題だけではなく、環境問題・気候変動にも多大な影響を及ぼす恐れがあることが示されました。
例えば有害物質やバクテリアが土壌や地下水を汚染する可能性があります。また、医療用品に多く使われるプラスチックの不完全燃焼により、ダイオキシン等が放出され、気候変動や人類健康が脅かされます。
そのような悪影響を回避するため、厳格な分別、漏れ防止を備えた専用運搬車両、高温蒸気処理など新たな処理手順が求められています。

発表している張志栄氏
三人の発表者の発表に対して、龍谷大学政策学部教授櫻井次郎先生、中国訪問団リーダー李力氏が、コメンテーターとして解説を行いました。また、あおぞら財団理事長村松昭夫先生、オンラインで参加してくださった公立鳥取環境大学の相川泰先生からもコメントや質問をいただきました。
中国人がご馳走をする時「料理が余ることが、誠意の証である」という伝統的な考えがある中、現在の「完食」ブームの広がりをみると、食への考え方の変化してきているようだ。湿地と共生する地域住民の環境保全意欲が培われたきっかけと活動のモチベーションの維持の仕方は?。一般市民が医療廃棄物に関する認知を向上させる方法は?などについて、議論が盛り上がりました。

参加者と発表者が議論している
あおぞら財団が来年、設立30周年を迎えるこの時期で、中国の環境NGOとの交流も15年目になりました。
かつては、深刻な大気汚染でどんよりとした北京の空の下で、車が昼でもライトをつけなければ走れない光景が、もはや過去形になったそうです。この間、日中交流・研修でのつながり・学びが中国の環境NGOの一助になっていれば幸いです。
また、長年の交流の中で、中国環境NGOの成長の速さも見られました。環境問題の観測・解決にドローン技術、AI分析などハードウェアを活用したり、環境地図アプリを開発し、一般市民に呼びかけ、まちの環境状況をアップしてもらうなどのソフトウェアにより市民参加を促すような環境対策が、逆に現在日本の環境NPOが参考すべきところではないかと考えられます。
厳しくなりつつある日中関係の下で、活発な民間交流によって、友好な国際関係を維持することが大切だと思います。また、国境を超える環境問題・気候変動問題に関して、必ず国と国の手を組まなければ解決できません。
日中環境問題サロン、次の15年に向けて、引き続き、交流活動をよろしくお願いします!

集合写真
(記・あおぞら財団アルバイト 王子常)
========================================
アジア各国では、現在進行形で、様々な公害・環境問題が発生しています。
その中で、自分たちの住み暮らす地域の環境を良くしていこう!と取り組む人々がいます。
あおぞら財団の国際交流活動を通じてつながったアジア各地の環境活動を報告・紹介するページ「アジアの環境活動でつながろう」を新たに作成しました。
それぞれの取組みを知り、学び、つながることで、活動の輪を広げていきましょう。
ぜひ↓ご覧ください。