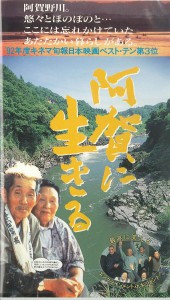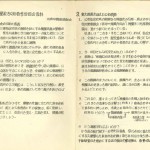新潟水俣病・阿賀野川と共に-映画『阿賀に生きる』-
(資料館だより30号、2010/05)
紹介資料:映画『阿賀に生きる』(1992年)
エコミューズでは、今年8月5~8日、新潟水俣病の現場を訪ねるスタディツアーを開催します。そこで今回はエコミューズ所蔵の映像資料のなかから、新潟水俣病の被害地域である阿賀野川流域に暮らす人々の生活を追ったドキュメンタリー映画、『阿賀に生きる』(佐藤真監督、カラー115分、VHS、1992年)を紹介します。
新潟水俣病は、昭和電工鹿瀬工場から阿賀野川に流された、メチル水銀化合物を含む排水によって引き起こされた公害病です。患者は手足のしびれや運動障害など、さまざまな症状に苦しみました。水質汚染による漁業への影響も深刻でした。
映画は、阿賀野川と共に生きる人々―米作りを続ける老夫婦、川風を知り尽くした川船頭、川舟を作り続ける老大工、餅つき職人の老夫婦に3年間密着して撮影されました。川筋に暮らす人々の、なにげない日常。そしてそのなかで、患者会活動や未認定患者問題など、新潟水俣病と向き合う姿が映し出されます。それは決して外側から眺めるだけでは伝えることの出来ない、公害地域の「今」を捉えた映像です。
現地を歩き、生の声を聞き、新潟水俣病の「今」を知って、伝えたい―スタディツアーを前に、そんな思いを新たにする映画です。
☆資料館だより30号はこちら
(エコミューズ資料整理スタッフ 森本)