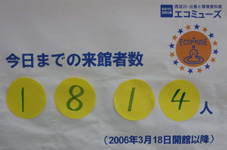あおぞら財団も参画している地域資料シンポ実行委員会のシンポジウムを開催します。
■地域資料シンポ拡大研究会(通算第2回)■
(地域資料研究会2010年度第2回と共催)
自治体文書館が目ざすべき道
—公文書管理法施行をひかえて—
地域資料シンポ実行委員会では、本年4月の公文書管理法施行とここ数年取り組んできた大阪府・市公文書館問題をにらんで、今回、下記の拡大研究会を企画しました。
今回は、神奈川県立公文書館の石原一則さん(内閣府の公文書管理委員会のメンバーでもあります)をお招きして、神奈川県での長年の経験、公文書管理法の内容や課題、現在進行中の国による公文書管理・公開体制の準備状況などもふまえ、今後、自治体文書館が目ざすべき方向性について論じていただきます。
あわせて実行委員会からの問題提起では、大阪府・市公文書館問題の最新の状況についても紹介し、大阪地域における今後の課題について議論したいと思います。
ふるってのご参加をお待ちしています。
日時 2011年3月12日(土) 17:30〜20:00ごろ (*開始時間にご注意ください)
場所 キャンパスポート大阪(大学コンソーシアム大阪)(電話:06-6344-9560)
(地下鉄梅田駅またはJR北新地駅下車、大阪駅前第2ビル4階) 右下の地図参照
URL→http://www.consortium-osaka.gr.jp/about/access.html
内容
・問題提起:地域資料シンポ実行委員会事務局
「大阪府市公文書館問題の到達点と課題」
・メイン報告:石原一則氏 (神奈川県立公文書館・公文書管理委員会委員)
「公文書管理法と神奈川県立公文書館」
*終了後、ささやかな懇親の場をもちます。
主催 地域資料シンポ実行委員会
(構成団体:あおぞら財団、大阪歴史科学協議会、大阪歴史学会、西山夘三記念すまい・まちづくり文庫、地域資料研究会)
連絡・問い合わせ先:
地域資料シンポ実行委員会事務局
〒558-8585 大阪市住吉区杉本3-3-138
大阪市立大学大学院文学研究科 日本史学教室
(大阪歴科協研究委員、佐賀 朝、06-6605-2398)