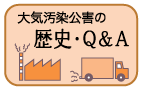インタビュー 被害者を「灯火」として 1998年10月
|
森脇 君雄 全国公害患者の会連合会幹事長 (財)公害地域再生センター理事長 |
傘木 宏夫 (財)公害地域再生センター研究主任 |
|
傘木 |
本日は、これまで全国公害患者の会連合会とアジアの公害被害者や環境NGOとの交流を通して、日本の公害の経験とはいったい何だったのだろうかということを、森脇さんのお話を聞く中で、整理してみようと思います。
まず、森脇さんはどうして、公害被害者救済運動に関わるようになったのですか? |
苦しむ姿を見つづけてきた-ひどかった六○年代の公害-
|
森脇 |
日本の大気汚染の状況は、昭和三○年代後半から四○年代にかけて、本当にひどいものでした。ばい煙のため、昼でも二、三メートル先が見えず、車は昼でもライトをつけないと走れないとか、運動会や夏祭などもできないという時がありました。そういう状況の中で、公害被害者がどんどん出てきました。
私が公害のひどさを知ったのは、一九六一年頃でした。工場から色のついた煙や、悪臭を多量に出している時代でした。その時に、工場と交渉したりするのは結構あったわけです。でもそれは、公害をなくそうというものでした。その頃は、まだ被害者がいても被害者を救済するとか、組織するというようなことは、私はあまり考えていませんでした。 一九六七(昭和42)年に西淀川区にある淀川勤労者厚生協会というところに就職したのですが、そこが大和田地域という所に病院建設をすることになったんです(後の千北病院)。地域の方からお金を寄せてもらって病院を建てるわけですが、いろいろな形で地域との連携をつくる活動を行いました。その中で子どもたちとソフトボールをやっていたのです。ところが、一人だけずっと座ってみている子がいました。他の子に話を聞くと、「あいつはぜん息もちで、ようバットふられへん。学校にもあんまり来てない」ということでした。それが小谷信夫くんでした。「みんなとソフトボールやろう」と言って、小谷くんにバットを振らせたら、三振でしたがすごく喜んでくれました。 その後私が、「あー、水が飲みたいな」と言ったら、小谷くんが僕の袖を引っ張って、公園のすぐ側の自分の家へ連れていってくれました。 家の畳を見ると、それがひどかったんです。畳に血がずっと続いている。黒くなっている血と赤い生々しい血、それから白くかさかさになっている畳の目がありました。夜中にぜん息の発作が出て、苦しみの余り畳をひっかく。おもいっきりかきむしるから生爪の間から血が出て、それが畳の間に入って、血だらけになっていたわけです。これは何とかしなくてはと思ったのが、被害者運動と関わるきっかけでした。 その後病院が出来上がり、被害者組織の活動を始めるようになると、いろいろな子どもたちと知り合うようになりました。 出来島のAさんの場合は、補償法(公害健康被害補償法)ができて治療費が出るようになるまでは、主人と患者である子どもにだけ魚や肉を与え、自分は「肉や魚が大嫌い」と言って食べなかった。子どもの治療費が大きくて生活が苦しかったんです。 また、小谷くんは中学では体が弱いというだけで特殊学級に入れられていました。学校の水泳の時間には、いつ発作が出てもわかるように、彼だけが違う色の帽子をかぶらされていました。 南竹照代さんの場合、肺気腫で肺の中に空気が入らず、それでも勉強がしたくて、入院中も一生懸命やっていましたが、二四才で亡くなりました。 南竹さんと同じクラスだった網城千佳子さんは、一九才の時、アルバイトの帰りに尼崎の駅で発作をおこし、そのまま窒息して亡くなりました。 そういう苦しみをいっぱい見てきました。だから、この子たちのためにも、医療をやらないといけない、公害を何とかしないといけない、と活動してきたわけです。 |
患者自身が勝ち取った要求-大きな意義をもった四日市裁判-
|
傘木 |
当時は病院関係者も含めて、小谷くんのような症状を見ても、一般に
公害による健康被害だという認識が広まっていなかった、ということ ですか? |
|
森脇 |
そうです。煙の街、それはつまり繁栄の街という時代でした |
|
傘木 |
認識が広まってきたのは、いつ頃からですか? |
|
森脇 |
一九七二(昭和47)年に四日市判決がありました。これは加害企業に対して公害被害者への賠償を命じるという画期的な判決でした。この時初めて、被害者としてまとまって運動することの重要性を知ったんです。 |
|
傘木 |
四日市の判決というのは、すごく大きな意義があったと思います。この判決を勝ち取った背景には、色々な分野の調査研究や住民の運動があったと思うんです。その中でも、公衆衛生関係の人たちの役割が大きかったと思うのですが。 |
|
森脇 |
大きいですね。西淀川の場合、一九六四(昭和39)年くらいから疫学調査を実施して、一九六九(昭和44)年に特別措置法(公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法)を出したわけですから、公衆衛生関係の方の活動はすごい力になったと思います。ただ、この特別措置法は、与えられたもので、公害患者自らが動いて得たものではなかったのです。
一九七二(昭和47)年十月に西淀川公害患者と家族の会が作られました。一九七三年三月に企業の責任による救済制度を作るというので、二○○人ほどが集まって、大阪市役所へ座り込みに行きました。ちょうど市議会で民生委員会をやっている真っ最中で、夜の十一時頃まで座り込みました。多くの人が途中で倒れたけれども続けました。 そして三か月後の六月、一九七三年の四月一日に遡って、企業から拠出される金を使って、被害者を救済するという制度が作られました。これは大阪市内では西淀川だけの制度でしたが、尼崎、千葉、川崎、四日市などでも、公害患者自らが制度を勝ち取っていきました。 |
|
傘木 |
自治体としての制度ですね? |
|
森脇 |
そうです。自治体独自の制度の広がりや、四日市判決などがあって、国としても制度を作らないといけないということになり、一九七三(昭和48)年に入ってから、被害者と国との折衝が始まりました。そして十月に公害健康被害補償法(公健法)ができ、翌一九七四(昭和49)年九月一日から施行されました。これは患者自らが制度の上で勝ち取ったものですし、その中には住民要求・患者の要求がいっぱい入っています。与えられたものではなく、患者自身が勝ち取ったものだという意識があるのです。 |
専門家と協力して-公害病患者の掘り起こし-
|
傘木 |
これは医学関係者や法律家、それから制度を作り、実務を担う行政関係の人たちが一緒にならないとだめですよね。疫学調査は医学だけではだめで、環境がどれだけ汚染されてるかを把握しなければいけない。気象条件、発生源の断定など、いろんな科学者の存在や連携があって、初めて公害被害者というものを明らかにしていくことが出来たのですね。 |
|
森脇 |
私たちが運動を始めたときには、西淀川医師会は「患者の立場に立って診療する」ということで、患者会結成にはお医者さんとの協力がありました。それで、患者さんを組織することが出来ました。 |
|
傘木 |
日本は自由開業医制度で、しかも国民皆保険制度を持っていた。そういう制度があることによって、患者を日常的に診療する主治医の協力を得て、早期に見つけ出すことができたという側面があったと思います。 |
|
森脇 |
私たちは恵まれてたと思います。日本では、お医者さんが患者のためになる仕事をしようという点で、アジアの国々と違っていました。
もう一つ、地方自治体の力というものも結構あります。大阪でも、四日市でも、地方自治体が先に調査して発表、国へあげていくという流れがありました。日本では、公害によって自治体が民主化したという部分も結構あると思います。 また、日本では労災や生活保護など一つずつ制度を確立して、それぞれ狭い範囲だけれども生活全般を補償するというふうにしてきました。それには、弁護士の協力と、制度論の確立がどうしても必要でした |
|
傘木 |
医療制度や法律制度、いろいろな支援や公衆衛生の方の取り組みなどがあって、今日の日本の公害患者の運動があるわけですね? |
|
森脇 |
国自身が公害患者というものを認めましたしね。だから、補償法に認められた患者というものは、誰からも反論できない、確立したものです |
被害者をどう守り、組織するか-被害者は運動の灯火-
|
傘木 |
各国の公害が大変だと言っても、かつての日本のような、極端な公害による極端な健康被害という状況ではなくなってきています。でも、公害の広がりという点では、環境ホルモンのような問題も含めて、ものすごく大きくなってきていますよね。アジアでもそういう状況だと思うのですが、そういう中で、日本の経験を通して、何を語り継ぎ、どういう教訓を伝えることが必要なのでしょうか? |
|
森脇 |
私たちが昔味わったような部分は、まだアジアにはいっぱいあると思います。そこには日本の経験を十分に生かすことが必要だと思います
例えば、先日出された川崎判決では、自動車の排ガスや工場からのばい煙などに含まれるSPM(浮遊粒子状物質)やNO2(二酸化窒素)と健康被害の因果関係が明らかで、現在においてもそれが進行していることを認めました。車やいろいろなものがごちゃごちゃになって、公害の原因がわからないような状況の一方で、ぜん息患者は増えているというタイのバンコク市のような所。そこでは、川崎裁判での情報などを聞けばいいと思います。 また、被害者のことを追求することがどうしても必要だと思います。それから環境全体を良くするという運動も。 |
|
傘木 |
いろいろな国で特徴があり、違いもあるけれど、公害問題の深刻さという点ではどこも同じ。森脇さんはそういった国々でも、やはり被害者自身が公害が原因で病気になったということを認識し、組織されていくことが必要だと思われているわけですね。 |
|
森脇 |
そうですね。アジアの経済が大変な状況になってきて、被害者救済が後回しにされそうだけど、今のままで放置してはならないと僕は思っています。
被害者というのは、運動をしていく上での灯火だと思うのです。灯火がともっている間は、それを消さないために周りは運動します。被害者のない運動というのは、被害をなくすためというようになりにくいのですね。だから、被害者が出たら、その被害者をどう守っていくかという、火を消さない運動のためにも、被害者を組織していくことは大事だと思いますね。 |
因果関係をきちんとしないと対策もはっきりしない-大切となる因果関係の明確化-
|
傘木 |
被害者をきちんと掘り起こし、その被害者を救済し、そういった被害者が生まれないような環境を作っていくという活動をきちんと環境運動の中に位置づけていくということを、森脇さんとしては各国に訴えていきたいわけですね。
ところで、アジアの各国に共通しているのは、一九八○年代中期以降の民主化運動のうねりというものが、あらゆる環境運動の広がりの根底にあると思うのです。しかし、被害者運動として目に見えてこないのは、いま起きている健康被害というものはいろいろな汚染源が重なっているので、病名を明確にすることは非常に困難だということも聞きましたが? |
|
森脇 |
因果関係を明確にしなければ、企業を追求し、補償させることは出来ません。国の制度も同じことです。だから、日本では病名をはっきりさせているわけです。アジアの各国ではそれがないから、企業をしっかりと追求できないわけです。 |
|
傘木 |
病気の原因と被害の因果関係をきちんとしないと、対策もはっきりしないということですね。だから日本の場合は、 公害健康被害補償予防法というのは2種類あるわけですね。
一つは、イタイイタイ病や水俣病のような特異性疾患。病気を引き起こす原因物質と疾病の因果関係を特定できるものですね。 もう一つは大気汚染に伴う病気のような、非特異性疾患。本来は疾病を引き起こす原因が複数以上であり、原因物質を特定することが難しい病気ですね。これには、疫学調査を踏まえて、大気汚染のひどい地域に一定期間住むか、働いていて、指定された呼吸器の病気にかかっていれば、それは大気汚染が原因だとする、一種の”割り切る“というやり方をとっています。 公健法は税金を使わず、工場の煙の排出量に応じてお金を徴収するという制度ですね。だから、汚染物質を排出する量を企業が抑えれば抑える程、お金を出さなくてもよくなる。それで、環境装置をつけるなどの対策を取るようになってきたわけですね。 公健法の良い点は、患者さんの救済という点でも良かったけれども、工場の煙を抑えるという効果もものすごく大きかったわけですね。 |
|
森脇 |
まあ、そういう制度が出来て、制度上は企業が金を出したけれども、どこの企業が一番公害病を起こしたかはわからずじまいだったんです。
ところが、患者にとっては、企業が責任を認めてちゃんと謝ってほしいわけですね。その上で、損害賠償をしてもらい、今後の公害対策も勝ち取りたい、だから裁判を起こして、謝らせるまで闘いを続けるわけです。日本ではそういう裁判闘争を、患者、法律家、医者、科学者が一体となって続けてきたのですが、そのような運動は海外にはあまりないわけです。 |
患者自身の自覚が大切だった-運動の中で制度を作り、広げていった-
|
傘木 |
もちろん、アジアの国々は風土も違えば、伝統も違う。けれども、被害者を救済しなければならないということは、普遍的なことだと思います。だから、そのことの大事さを訴える森脇さん達の活動は、非常に重要な意義があると思うのですが? |
|
森脇 |
そういった理屈や仕組みを理解するだけでも大変だと思いますね。僕たちの経験でも、患者自身が、自分たちが公害によって病気になっているということを自覚するのに時間がかかるし、それを患者としてまとめていくのは、長い闘いでした。
一九七○(昭和45)年から七四(昭和49)年までの間は特別措置法(公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法)が適用されてきました。これは上から与えられたものであり、自分達が公害患者だと自覚しにくく、権利だと思えないわけです。被害者自身の要求によって補償制度を勝ち取った時(一九七四年九月施行)、自らの病気を含めて人に堂々と言えるようになり、制度の仕組みを胸を張って説明出来るようになったわけです。 |
|
傘木 |
それは、日本の民主主義の形成の上で大事な事ですね。自分たちがつくったという事を確信して、その制度を普及する先頭に立つと言うことですね。
尼崎の松さん(尼崎公害患者・家族の会会長)は、制度を普及するために自分でいろんな病院や診療所の窓口に行って、患者さんを把握するということをしていました。そうすると「自分は患者じゃない」「公害なんか関係ない」という人がやっぱりいるんですね。公害患者だと思われたくない人に、企業との関係も含めて説得していくということをやってきたわけです。そういう事があって初めて、制度が根付くのかなと思います。 公害患者が運動の中で制度を作り、それを自分たちで広げていって運動してきたという経験は、非常に重要なことではないかと思います。 |
被害という事実が始まりだった-被害者自らが立って、訴える-
|
森脇 |
運動している中で、ひとつ分かったのは、公害病がひどくて、重症の人ほどよく活動するということです。被害者同士の運動の中で、ひどい人が中心になったのが、この運動を支えてきたのだと思うのです。
例えば、集会用に看板を持っていこうという時、元気な人が持っていけばいいというのが普通。だけど、患者同士だと、一番ひどい人が持って行くわけです。そうしたら、元気な人は見かねて一生懸命手伝おうとする。これが運動を支える基本でした。そして、苦しみは自分だけでいい、子や孫に絶対残したくないという願いでやるから、結果として死ぬまで、生涯の運動になるわけです。 患者が「灯火」だというのには、そういう意味があるのです。その灯火があるかぎり、運動は広がっていくわけです。 もうひとつ、日本の公害被害者運動のなかで「公害被害者総行動」という活動があります。これは、大気汚染だけでなく、水俣病、イタイイタイ病、空港や新幹線の騒音、薬害、食品公害などの被害者が各地域のそれぞれの要求・課題を持ち寄り、環境月間である六月に、環境庁長官、各省庁の関係部局長、経団連などの財界と一斉交渉をするものです。これは、公害被害者の声を直接、大臣や財界に届ける場でもあります。このような取り組みを行っているのは、公害被害者だけです。一九七六年に始まったこの活動はすでに二三回を数えます。そして公害被害者の要求を解決し、前進させる大きな原動力となってきました。 |
|
傘木 |
すると、アジアにおける公害被害者の掘り起こしというのは、被害者を助ける、救済するというよりも、自分たちが立ち上がるということをいかに支援するか、またそこが立ち上がらないと、何も改善できないということですね。 |
|
森脇 |
その人が公害被害者だということを、科学的に判るようにしないといけません。学者の先生達はそれを支えてやらないといけない。運動を支えるのではなく、理屈や制度を支えるために、それぞれの専門をいかして患者と一緒にやるということが必要です。
自分が公害被害者だということを認めれば、自然と先頭に立つわけです。患者でない人が前へ出ると、被害が見えなくなってしまう恐れがあります。 運動はしんどいし、被害がひどいから過激になりがちです。でも、被害者はどんなことがあっても、過激になってはいけない。被害のひどさをとことんまで訴えていく中で、理解をしてもらわないといけません。淡々と被害を訴えて、周りを全部巻き込んで、変えていかないと被害者を救済しろとの世論になりにくいと思います。 被害者自らが立って訴えない限り、被害は分からないのです。 |
|
傘木 |
まず被害という事実があって、それを救済するための理屈は後からついてくるということですね。
ところで、森脇さんが原告団長をつとめる 西淀川大気汚染訴訟は、一九九五年三月に被告企業九社と和解し、今年(一九九八)七月には国・阪神高速道路公団との間にも和解が成立し、すべての裁判を勝利のうちに終結しました。 公害裁判というと、一九七○年代はじめの四日市大気汚染、イタイイタイ病、熊本水俣病、新潟水俣病のいわゆる 「四大公害裁判」が有名です。これらの裁判は被害者救済に大きな道を開きました。 一九八○年代からの大気汚染公害裁判は、西淀川が先導する形で、それぞれ解決に向かっています。西淀川方式といわれる和解のあり方は、どのような特徴があるのでしょうか? |
|
森脇 |
四日市の場合、裁判では勝ったけれど、勝利の日も工場の煙はモクモクと出てて、空気は汚れたままだった。それが私には印象的でした。
私たちの裁判は長期化を余儀なくされましたが、この間に公害対策や環境技術も進展し、一見して空はきれいになりました。しかし、大気汚染の種類も目に見えにくい複雑で危険なものに変わっているし、土地は汚染されている。街には緑やうるおいがない。そんな状態のままにしておいていいのか、ということを自問自答する中から、「地域再生プラン」というまちづくりの計画を被害者の立場から提唱したのです。 こうしたことが、被告企業や国との和解にも反映され、地域再生の取り組みに被告企業や国が協力するという流れを生み出したのです。きちんと過去に対する謝罪をさせて、そのうえでパートナーシップを組んで、地域の環境改善に協力しあうという「未来指向」の解決の方向を示したと思っています。 「未来指向」というのは大変なことです。まだまだ地域を良くしていくためのたたかいを続けなければいけないのですから。しかし、被害者の願いを少しでも現実のものとするために、これからも頑張りたいと思います。 |
|
傘木 |
あおぞら財団はそのために設立された団体ですから、森脇さんたちのそうした思いを大切にして、私たちも頑張りたいと思います。 |