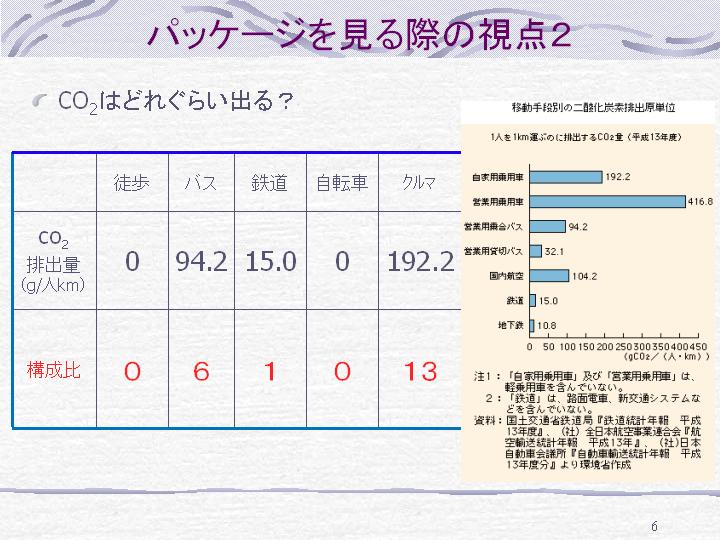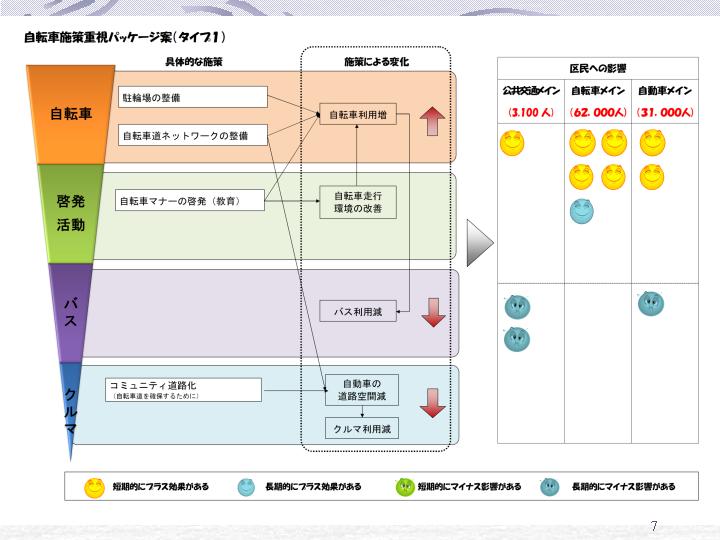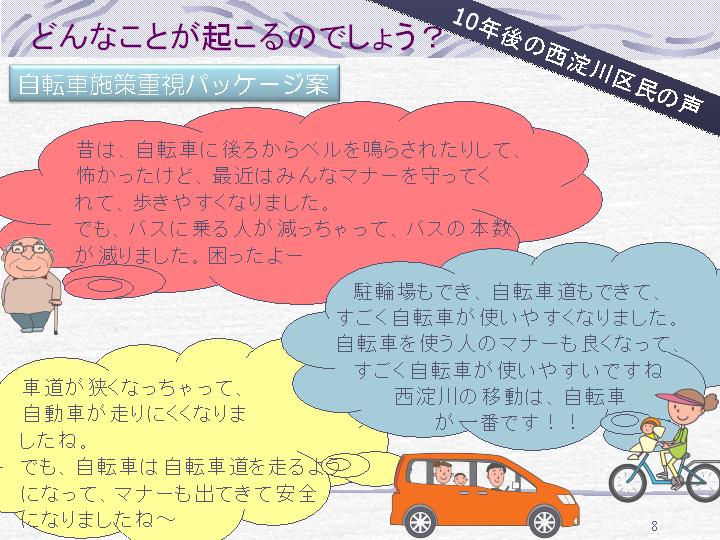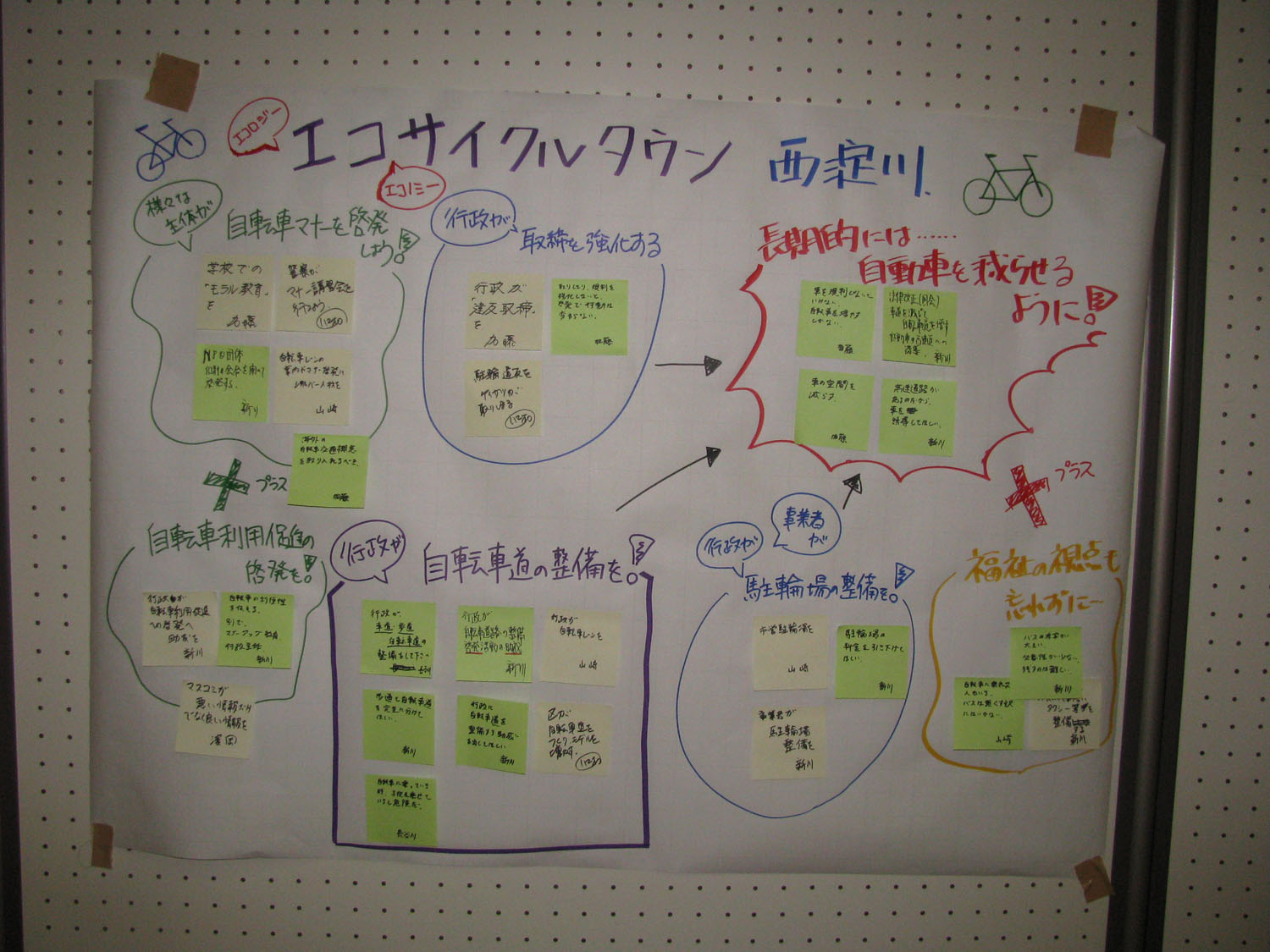あおぞら財団ボランティア実習生 大阪経済大学3回生 谷本 章和
8月22日水都大阪2009のキックオフイベントである「つるむde大阪」のツアーで大阪の街を自転車で回るというツアーにボランティアとして参加させてもらいました。参加者は16人で8人ずつのグループに分かれ、僕は先に走るグループの記録係をしました。朝9時半に東洋陶磁美術館前から出発しました。
天気予報には雨と書いてありましたが、今日はキックオフイベントということもあり雨がもし降っても今日は走りきると言ってみんな出発しました。東洋陶磁美術館の前の橋です。

東洋陶磁美術館を出発した最初の交差点です。

みんな一列になって走りました 。


ここはツアーが始まって最初の休憩した場所です。
大阪の歴史などについての説明も言ってもらえるので興味を持てると思います。

ここのオステリアをいうレストランは昔、消防署だったらしいです。
そのため、あの消防署の赤いランプが今も付けられています。

ここは今では、車が行きかう道路になっていますが、
江戸時代の初めには、西横堀と江戸堀の分岐点に撞木橋というT字型の橋があったらしいです。

上の写真の左下にある石碑です。

ツアーの皆さんが交差点で待っている時の様子を感じ を撮りました。

ここは放置自転車が多いなと思いました。
放置自転車が多いため走りにくく感じました。

ここは江戸堀川跡碑であり説明も入りつつ休憩していました。

その時のここがそこのみんなの風景です。
みんな真剣に昔の事について、聞いていました。

ここが次の休憩所靭公園であり、昔は戦闘機の滑走路だったと聞きました。

ここら辺の街は陶器を作っている店が多いと聞きました。



ここでも昔の水路の事についての話を教えてもらいました。

これが上の場所での石碑です。

ここが四ツ橋であり、今の大きな道路がもともとは水路であり4つの橋が東西南北に交差しており、2つの川に井桁状に架かっている珍しさから、浪速の名物であったらしいです。

今では車の交通量がすごい道路になっています。
ここ��
�話が、個人的にはすごい興味を持てました。

ここの道が僕個人的には、すごい走りやすかったです。

ここが今の西長堀駅です。


ここは西長堀で入居条件が厳しく、司馬遼太郎等の著名人も住んでいたらしいです。

三菱財閥のゆかりのある場所も見ることができました。

千代崎に着き、橋を上がった瞬間に大きな京セラドームが見えました。

市長さん等を乗せた水上バスがちょうどいいタイミングで来ているのが見えました。


市長さん等を乗せた水上バスがドーム前千代崎に着く様子です。

応援に来ていたバッファローズとチアリーディングの方たちです。

大阪市長さんが下りてこられたところです。


市長さん等による水都大阪のキックオフのテープカットをした所の様子です。

僕らもバッファローズのかわいいマスコットときれいなチアの方と
写真を撮らせてもらいました。

今回タンデム自転車という2人乗りの自転車があり、2人の呼吸を合わせないと難しいらしいのんですが、 大阪市長さんにタンデム自転車を乗ってもらいました。

自転車のツアー再開です。

12時前ごろに船着場に到着しました。

水上バスに乗った時のみんなの写真です。
みんな話とつまむdeスイーツに夢中です。

水上バスが走りだしました。

水上バスは乗ったことが無かったのですごく自然で楽しかったです。
橋の下を通る時などはすごく涼しかったです。

この写真に載っているものは有名な鍛冶職人が作ったものらしいです。

ここで水上バスはいったん停止です。

途中水門があるのですが、写真のように水を出して水門の両側の水の量を一緒にするらしいです。

赤いランプが青になるとまた水上バスが進みます。

中之島公園の様子です。

ここからは噴水が勢いよく出るらしいです。

水はやっぱり汚かったのでもっと綺麗になればいいのになぁと思いました。

水上バスから一瞬だけ大阪城が見えました。

ここは昔、戦争の頃、ここから戦争に必要な物資などを運んでいたらしいです。
大阪城港に水上バスが着き、今日ツアーを緒に参加した人達みんなで記念撮影しました。
雨も心配されていたけど降らず、いい感じでツアーを回れました。
このツアーを参加して、普段見ることの出来ない角度から大阪を見ることが出来、楽しく大阪について知ることができ、参加して良かったです。ママチャリの自転車でも参加できるので、気軽に自転車が好きな人、大阪を好きな人、大阪を楽しく知りたい方などはつるむde大阪のツアーの参加をお勧めします。ボランティアとしてツアーに参加させてもらって良かったです。