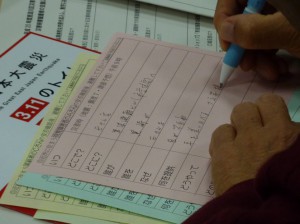●日 時 2014年1月25日(土) 10:00~12:00
●場 所 西区民センター ホール
●主催 公益財団法人公害地域再生センター(あおぞら財団)
●協力 西区役所 ●手話通訳協力 西区手話サークルながほり
1月25日、西区にて災害時要援護者支援セミナーを開催しました。
西区は、南海トラフ地震発生時の被害想定が大阪府下で最も大きいとされており、防災に対する関心が高まっている地域です。参加者は約30名でした。
最初に、「地域みんなが助かるために」と題して、栂紀久代さん(プチハウスなな)を講師に迎え、災害時要援護者支援についての講演を行いました。
まずは、要援護者の定義はについて聞きました。障がい者や高齢者だけでなく、子どもや妊産婦・日本語に不慣れな外国人、病気の人、負傷した人なども含まれている・・・“要援護者”と聞くと他人事のように受け止められがちですが、いつ自分や身近な家族が要援護者になるかわからない、という“自分のこと”として受け止めるところからスタートしました。
「地域を守るのは、地域です」という栂さんのお話の中で、自助、共助、公助の三位一体となった地域づくりや防災訓練の大切さを学びました。また、身につけることで「お手伝いして下さい/お手伝いできます」が目で見てわかるバンダナや医療バンダナなどの防災グッズの紹介、聴覚障がい者や車椅子利用者の介助方法、要援護者のトイレの問題などについても聞きました。
それから、当事者の方から「障害者の避難・日頃からのバリアフリーについて」のお話がありました。お二人とも、阪神淡路大震災の時の経験からまずは語られたのが印象的でした。
車椅子利用者である宮脇淳さんは、西区在住で、自分がここに住んでいることを地域の人に伝え、何かあった時は協力し合うことが大切、と話されました。防災訓練の時だけでなく、地域のつながり・連携を日々意識し、障がいの理解にもつなげていってほしい、ということでした。
また、鈴木昭二さんは視覚障がい者の立場から発言してくださいました。
鈴木さんは、どこまで介助したらいいか、まずは本人に声をかけてほしい、と話されました。避難所体験の訓練に参加した時、寝床からトイレまでの動線に点字ブロックのように道しるべを作ったら、初めての場所で介助者がいなくても一人でトイレに行くことができたそうです。一人ひとり、介助の方法や必要とされる介助もちがいます。声をかけて聞くことで、お互いがスムーズに動けます。参加者のみなさんも深く納得した様子で聞き入っていました。
次に、西区役所の市民協働課・防災担当の方より、西区の取り組みについての紹介がありました。
今力をいれているのが、津波避難ビルの指定と、災害時地域協力貢献事業所・店舗の登録ということです。避難場所に貼るステッカーのデザインを小学校に依頼したり、地域の人たちと協働した多様な取り組みが行われています。収容避難場所については、広報紙やホームページなどに掲載して情報発信が行われています。来年度は、小中学生と一緒に避難所開設訓練の実施を目指しているとのことでした。
その後、実際に要援護者の避難支援を体験しました。
視覚障害者の誘導体験は初めてという方がほとんどでしたが、参加者の中から希望があり、少し難しい階段の昇り降りも体験。みなさん積極的に参加されていました。
もう1つ、布製担架も実際に使ってみました。
使い方の説明を受けて、6名ずつのグループに分かれ、今回は5人で搬送する方法を実践しました。
担架にのっている人がどうやったら安心した気持ちでいられるかを思いながら、それぞれ声をかけあうことの大切さを体感しました。
最後に、参加者全体での意見交換を行いました。
手話で「大丈夫?」と尋ねる時は、どうしたらいいですか?とぃった質問も出され、参加していた聴覚障がいのある方から、その方法をみんなで教わりました。
「大丈夫?」と尋ねる手話と、「大丈夫です」と答える手話は同じで、強弱をつけることでその区別をつけるということです。また、相手の顔をしっかり見れば伝わる、それは健常者であっても障がい者であっても同じ、とのお話に、大事な気づきをいただきました。
会場では防災グッズの展示も行っており、熱心に質問したり、手に取って見たりしている人もいました。
開催後のアンケートでは、「支援する具体的な知識を得られて良かった」「どのように介助してほしいかを知ることが大事だと思いました」といった感想から、「マンションが多く、マンションが地震で倒壊しなければ非難せずそのマンションに居れば良いが、その際の連絡をどうするかを考えないといけない。連絡網便りを考えたいと思っています。停電の際のトイレの対応には色々なグッズが参考になります。」という具体的な実践につながる声も寄せられていました。
本事業は、「独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業」を受けています。
フェイスブック「みんなで守る!みんなで助かる!災害時の要援護者支援!」もあります。
(吉田)