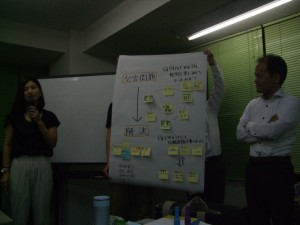2019年10月11日(金)、毎年恒例となっている司法修習生研修の受け入れを行いました。
今年は9名 6名の司法修習生と3名の弁護士の方が参加してくださいました。
午前中は、村松弁護士より「公害環境問題への関わり方~西淀川公害訴訟を中心として」と題する講義を受けました。
午後からはフィールドワークを行いました。
阪神出来島駅に集合し、43号線沿いと大気測定局を設置している出来島小学校を見学しました。
43号線で行われている、ロードプライシングによる交通流対策や二酸化窒素低減技術の試行といった取り組みについて説明しました。

ロードプライシングによってどれくらい効果(交通量の減少)があったか?という質問がありました。
看護小規模多機能型居宅介護施設・ソラエ(あおぞら苑3号館)で、辰巳代表にお話を伺いました。
辰巳代表からは、あおぞら苑やソラエのコンセプトや想いをお聞きしました。

医師と弁護士によって支えられている面があるというお話があり、
「現場の気持ちがわかる弁護士さんになってほしい」とのメッセージがありました。
その後、公害病患者の治療の拠点となった千北診療所、あおぞら苑を巡り、
大野川緑陰道路を歩いてあおぞらビルへ向かいました。


あおぞら財団に戻り、西淀川公害患者と家族の会 語り部・前田春彦さんのお話を聞きました。
働きたくても働けなかったことや、公健法の補償の重要性、「できることはやってみよう」と思い、語り部活動に参加していることについてお話がありました。

「裁判を通じて、一番叶えたかったことは」という質問には、
「空気をきれいに。しかし、今でも車の排気ガスや工事にともなう臭いや煙が気になるので、もう少しマシになればよい」とのお答えがありました。
資料館見学後、藤江事務局長から西淀川公害裁判の概要とあおぞら財団のあゆみについて説明がありました。

和解金の一部をもって設立されたあおぞら財団の現在の活動と役割について、
公害反対運動を引き継ぐというより、パートナーシップの橋渡しであるということ、
公害患者さんがどんどん亡くなっている現在、今後どう伝えていくか、また現在日本が抱えている環境・公害問題にどう関わっていくかが課題であるとしました。
公害患者と家族の会・上田敏幸事務局長からは公害訴訟の経過についてお話していただきました。

患者会で実施した勉強会で実際に使用した、上田さん手づくりのスケッチブックで説明していただきました。
「患者さん達ができるだけ安心した状況で結果を受け止められるように」という思いで和解に至ったこと、和解は「人生においてすばらしいできごと」だったということです。
質疑応答では、「活動のゴールは。何をめざしているか」という質問がありました。
上田さんからは「患者会が世の中の役に立つということは本来は無いほうが良い。藤江事務局長にバトンタッチすることはあってもゴールはない。乗り換え乗車駅にどう辿り着くか。」
藤江事務局長からは「『良い町にして』という患者らの望みを聞いて、防災などの活動に取り組んできた。住んでいる人がこれからの西淀川の町を作っていくためにも、公害のことを知り、患者らがやってきたことを知ってほしい。西淀川の町を良くするために患者らがやってきたことが残ると良い。「良い町」とはどんなものか、ゴールはない」
とそれぞれ想いを語ってくれました。

「具体的なイメージを抱けない若い世代に伝えたいこと」という質問には、
「まず教員が知らない時代になっている。何かあったときに自分で考えて行動できる子になるよう育ててほしい。その素材・土台に西淀川がなれればよい」
参加者の方からは、
「当時の状況を考えると、はじめの一歩を踏み出すむずかしさがある。常識にとらわれず、『そこに被害があるから』が原動力になったと感じた。そういうときに動ける弁護士になりたい」
「社会や企業からの被害は、知らない間に被害を受けていることがある。そのような被害者を泣き寝入りさせないように法律家として常にアンテナを伸ばしていきたい」
などのふりかえりがありました。
弁護士の卵の司法修習生という、これからの社会を担う人々に、公害についてしっかり学んでもらえることができ、今日学んだことを公害を起こさないような社会づくりに繋げてもらえるのではないかと思います。
研修受け入れについて詳しくはこちら → 研修受入