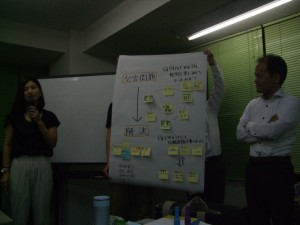あおぞら財団では、環境省職員を対象とする西淀川・尼崎地域における環境問題史にかかる現地研修の受け入れを行っています。今年度は10月17日から18日にかけて実施し、環境省職員の方16名、環境再生保全機構の方2名、合計18名が参加しました。
1日目は、オリエンテーションや自己紹介のあと、「西淀川公害、あおぞら財団について」を当財団の鎗山が紹介し、その後、公害患者の語り部である、須恵鷹雄さんと須恵佐與子さんから昔の西淀川の様子や病気や生活の苦しみ、現在の活動についてお話がありました。
次の場所を「西淀川・公害と環境資料館(エコミューズ)」に移して、森脇君雄さん(西淀川公害患者と家族の会会長)、上田敏幸(同会事務局長)さんから公害反対運動や環境省とのかかわり、公害健康被害補償制度についてお話がありました。

さらに「大気汚染公害訴訟が環境政策に果たした役割」として、村松昭夫理事長から講義があり、最後に今日のふりかえりということで、「今日の学び・印象に残ったこと」「もう少し深めたいこと・考えたいこと」を参加者がそれぞれ出し合い、グループ分けをしました。このグループごとに2日目のプログラムに取り組むことになります。
2日目はまず、尼崎と西淀川の工業地帯をバスで見学しました。
ロードプライシング等の大気汚染の現状について実際に確認してもらいました。
途中、国土交通省大阪事務所の方から43号線における高活性炭素による大気浄化をはじめとする大気汚染対策について説明を受けました。
みなさん熱心に耳を傾けられ、質問も多く出されました。
その後、看護小規模多機能型居住介護施設ソラエを見学し、
辰巳代表から、ソラエのコンセプトや想いについてお話をお伺いしました。
昼食後はあおぞら苑、大和田街道、大野川緑陰道路をめぐり、西淀川の町を体感してもらいました。
大野川緑陰道路では、これまでの研修内容をふまえて住民の方にインタビューしてもらいました。
みなさん積極的に地域の方にお話を聞いてくださいました。
あおぞら財団に戻り、藤江事務局長から西淀川の現状と地域再生のまちづくりについて、講義を受けました。
質疑応答では「海外に何を伝えるべきか?」という質問がありました。
藤江事務局長は、「技術的なことは伝えているが、社会制度や意識の面から取り入れられない。ここ(意識を変えること)を訴える必要があるし、興味を持たれるところでもある。住民らの向き合い方や被害者が声をあげる重要性について伝えていく必要がある」としました。
あおぞら財団理事の山岸さんからは、企業サイドからみた西淀川大気汚染公害訴訟についてお話していただきました。
企業の訴訟担当としての思いや和解に至った経緯を教えてくださいました。
法が整備されていない中でいろいろな課題が出てくること、そのようなときにどうするべきか考えてほしいと問いかけや、あおぞら財団の使命として、和解の精神を風化させないでほしいといったお言葉もありました。
企業の法務担当としての苦労や、和解に至るまでの実情、そこからあおぞら財団の理事となるまでの経緯について質問があつまるなかで、「知識と人間力を磨いて業務に生かすこと」、「相談者からの依頼に真摯に対応するだけでなく、どのような人か向き合うこと」が重要であると仰っていました。
最後に、グループワークで2日間のふりかえりを行いました。
それぞれのグループが設定したテーマについて、知れたこと、気がついたことを共有し、
積極的な意見交換が行われました。
公害問題が解決に至るまでをふりかえり、国はどのような役割を果たすべきだったか、どのようにして信頼関係を築いたかについて整理した班、行政としてなにができるのかを「政策」と講義のキーワードとなった「人間力」の観点から整理した班などがありました。
行政としてどのようなことができるか、またどのような「人間力」「対話力」が必要かといった点に注目した班が多かったようです。
また、インタビューした内容をもとに、実際に体験した高齢の方と公害経験のない若い世代を比較し、「どのように伝えることができるか」「何を伝えるべきか」も論点となっていました。