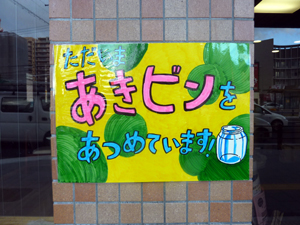日時:2010年12月4日(土)9:30〜12:30
天候:快晴&強風

探鳥会では、鳥のことだけではなく、植物のこと、
昆虫のことなど、いろいろなことを知ることができます。
野鳥の会のメンバーが歩く道々、見つけたものを
解説してくださいます。
しかも、その解説に、おもしろおかしい(?)コメントや
ダジャレが入っていると、頭にインプットされやすいので、
私は好きです。
【メタセコイア】
「アブラゼミは、なぜかメタセコイアが好き」
メタセコイアの木には、アブラゼミの抜殻が発見される
ことが多いそうです。
「なんか、おいしいもんでも、出とんのちゃうか」と
解説の人はおっしゃっていました。なんやろ?おいしいもんって。
【彼岸花】
「こいつは、みんなと違う生き方をしている。
みんなが枯れているときに、こいつは、青々としている。
だから、中国では忌み嫌われたりもする。
でも、みんなと同じ生き方をしてると、みんなが死んだら
自分も死んでしまう。
みんなと違う生き方をしていたら、みんなが死んでも
自分は生き残れる」
(なんか、コワー)

彼岸花は、田んぼのあぜ道によく生えていますが、
これは、根っこに毒があるので、モグラやネズミを寄せつけない
効果があるそうです。中国からお米といっしょに日本に伝わった
とのこと。
【ウバメガシ】
ウバメガシの葉っぱを、両目に当てたら、ほら、「姥の目」!
なんです。葉っぱがシワシワなんで、お婆さんの目のよう(?)

【ヒトモトススキ】
「これは、海岸近くに生えている。
帰ってから、インターネットで調べてみぃ!」

ということで、調べました。
おもしろい。割りにどこにでも生息しているのに、
東大阪市では天然記念物に指定されているそうです。
なんでも、昔の海岸の位置を示す指標になっている
からだそうです。
今回は32種の鳥が確認できました。
そして、いよいよ、ホシハジロが多くなってきました。
「星の数ほどホシハジロ」
・・・こうやって教えてもらってから、この鳥の名前を
忘れないようになりました。ダジャレは偉大なり。
カンムリカイツブリ、カワウ、アオサギ、ヒドリガモ、オナガガモ、ホシハジロ、
キンクロハジロ、スズガモ、ミサゴ、トビ、チョウゲンボウ、オオバン、イソシギ、
ユリカモメ、セグロカモメ、キジバト、ヒバリ、ハクセキレイ、ヒヨドリ、モズ、
ジョウビタキ、シロハラ、ツグミ、ウグイス、シジュウカラ、メジロ、アオジ、
カワラヒワ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス
次回は2011年1月8日(土)9時半からスタートします。
※いつもは第1土曜日ですが、このときは第2土曜日です。
参加希望の方は阪神なんば線「福」駅にお集まりください。
◎日本野鳥の会大阪のHPはこちら
鎗山善理子(あおぞら財団)