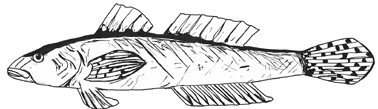2008年1月5日(土)
2008年が明け、正月気分のまま、
福駅(阪神電鉄西大阪線)に9:30集合。
新年スタートにふさわしく、天気もよく、22名の方が参加されました。
緑陰道路を抜け、途中で、樹木の話も伺いつつ、淀川に向かう。
淀川には、カモメが正月休みなのか、集合してました。

川岸には、ヒトモトススキが生えていました。
海岸に生えるそうですが、こういう所では非常に珍しい植物とのこと。
教えてもらわないと、通り過ぎてしまいます。

さらに、矢倉海岸に向けて歩いていくと、工事が行われていました。
看板には「西島地区高潮対策工事」と書かれていました。
以前、ウナギの仕掛けがあった辺りですが、矢倉公園とつながるのでしょうか?

河口には、ホシハジロが集合中。神崎川河口辺りには、2000〜3000羽はいるそうです。

今日は、ミサゴが水面に向けて降りてきたなあと思ったら、
魚(ボラ?)を捕まえる瞬間(魚が大きすぎて落としていましたが)を
見ることができました。思わず見とれてしまい、写真はとれませんでした。
本日、観察した野鳥の種類は、30種類。
ハジロカイツブリ、カンムリカイツブリ、カワウ、アオサギ、オカヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、ミサゴ、トビ、イソシギ、ユリカモメ、セグロカモメ、キジバト、ヒバリ、ハクセキレイ、ヒヨドリ、ジョウビタキ、イソヒヨドリ、ツグミ、メジロ、ホオジロ、カワラヒワ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ホオジロガモ
皆さま、お疲れさまでした。本年もよろしくお願いします。
次回は、ガン・カモ調査が1月15日(火)に開催されます(10:00福駅集合)
記:あおぞら財団・藤江