5月31日に行われました、ダンデム自転車試乗会のレポートを2ついただきましたので,掲載します。
———————————————————
5月31日に自転車タウンづくりの会主催の“タンデム自転車試乗会”に参加させてもらいました。
参加者は全員で9名。そのうち2名が全盲の方でした。 
9時30分に兵庫の門戸厄神駅で集合し、徒歩でタンデム自転車を貸してもらう「笹舟倶楽部」という喫茶店まで移動しました。
途中、道を間違えるといったハプニングもありましたが、程無くして到着!!
そこで少し休憩したあと、いよいよメインのタンデム自転車に挑戦ですっ(・ω・)/
タンデム自転車はロードバイクのものと、ママチャリ風の普通のものと2タイプに分かれていました。
私は同じ大学の友達とペアで乗りました。
ロードバイクに乗ったことが無いので、始めは一人で乗る練習からその道のプロ(笑)に教わりました。
最初は怖くてぎこちない走行でしたが(主に私が…)、何度目かでようやく様になってきました\(^o^)/
慣れたらこっちのもんです。
その後、実際に2人で乗ったときも、始めはぐらつきましたが、そのうち楽しめるほど余裕が出来るぐらい上達しました。
タンデム自転車おもろいです(´∀`)
基本インドアな私なのですが、それがまた乗りたいな~と思えました。
視覚障害者の方々はそれぞれ幹事長の藤江徹さんと井上守さんがつき、後部サドルに乗って走りました。
「実に40年ぶりに自転車に乗りました。」
とのこと。自転車に乗っている最中でも緊張ぎみな様子でしたが、積極的に自転車に乗ったり、終わったあとも笑顔で話されていたので楽しまれてなによりでした。 
タンデム自転車は大阪では乗れないのが残念ですが、ぜひ機会があるならまた乗りたいです(´ω`)
大阪国際大学 人間健康科学科 竹本 愛
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
5月31日にタンデム自転車の試乗会がありました。
門戸厄神駅前に集合し、喫茶店の笹舟倶楽部に移動 こちらの喫茶店でタンデム自転車をお借りしました!!
初めに、タンデム自転車を運転する練習をしました。
練習後は、広い道へ移動しました。
広い道では、快適にタンデム自転車で走ることができました。


ダンデム自転車で走った後、再び喫茶店に戻りました。
喫茶店で休憩し、その後、皆さんで記念写真を撮りました。
そして、駅に戻り、解散しました。
初めてのことばかりで、とても濃い一日となりました。
大阪国際大学人間健康科学科 安藤
———————————————————-
笹舟倶楽部HPはこちら→ http://www.sasafune.com/
つるむde大阪HP(今夏にタンデム自転車試乗会開催予定)はこちら→ http://www.tour-de-osaka.net/
記事一覧
タンデム自転車試乗会(5/31)
イ病・スタディツアー事前勉強会in関東
都留分科大学にて
「公害地域の今を伝えるスタディツアー2009
〜富山・イタイイタイ病の地を訪ねて〜」の
事前勉強会を開催

あおぞら財団では8月4日〜6日に実施する
「公害地域の今を伝えるスタディツアー2009
〜富山・イタイイタイ病の地を訪ねて〜」の参加応募を
おこなったところ、多くの方にお申込みいただき、
おかげさまで定員になりました。
たくさんのご応募、ありがとうございました。
そこで、現地に行く前にイタイイタイ病のことを事前に
勉強していただく機会として、事前勉強会を
関西および関東で開催しました。
関東では、2009年7月19日(日)に都留文科大学にて開催。
参加者は14人でした。
大阪での勉強会(7月12日)に引き続き、
畑明郎・大阪市立大学特任教授(環境政策論)
にイタイイタイ病や土壌汚染、カドミウム米の問題などについて
レクチャーをいただきました。
その後、インタビューの心得などを、高田研・都留文科大学教授/
あおぞら財団理事がおこないました。
そして、参加者の自己紹介。富山出身の人、韓国からの留学生、
教科書での「公害」の扱われ方に興味のある人など、多彩な面々です。
畑先生のレクチャー終了後の質疑では、行政の責任のあり方、
韓国での状況などにも話が及びました。
また、高田先生からのインタビューの心得としては、
話し手が語る内容は、あくまでも話し手の記憶を通じた事実で
あること、記憶があいまいなこともあるので、年代などに注意
が必要、といったことがありました。
畑先生のレクチャーから思うのは、イタイイタイ病の問題は、
医学、工学、法律、環境など、本当に多岐にわたるということ。
それだけ、全体像をとらえるのはとても困難かもしれません。
でも、自分なりの視点で、何かのとっかかりが今回のツアーでつかめると、
それが次へとつながっていくと思います。
また、カドミウム汚染米のことを聞くと、私たちの生活にとても
身近な問題だと思いました。
そして、中国の「ガンの村」で撮影された川の写真には、その川面の
異様な赤い色にショックを受けました。
身近で、かつグローバルな問題なのだとあらためて思います。
さて、とにかく8月のツアー、成功しますように!
鎗山善理子(あおぞら財団)
※本事業は(独法)環境再生保全機構の地球環境基金の助成金を得て運営しています。
韓国でフードマイレージ買物ゲームが紹介されました
韓国の京郷新聞でフードマイレージ買物ゲームが紹介されています。
http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=200808180232335&code=920401
昨年の6月11日に取材を受けていたのですが、
記事になっていたことを知らず、
今年の2月にあおぞら財団にやってきたグリーンコリアの方々に
「新聞で見た」といわれてびっくりしていました。
6月に韓国の司法修習生が研修できた時に、
新聞記事を見つけたら教えてくださいとお願いしたところ
律儀に、URLを教えてくれました。
感謝感謝です。
(林)
あおぞらビルにてコミュニティカフェを開催
体験型コミュニティカフェ
「てつ子の部屋」
あおぞらビルにて開催!
7月19日、13:00 あおぞらビルにてコミュニティカフェが開かれた。
主催は大阪経済大学学生によるサークル『緑のまちづくりサークル「ミアイ」』である。「ミアイ」は、昨年度まで大阪経済大学現代GPの活動で、環境問題について様々な取り組みを行ってきた学生実行委員のメンバーが、立ち上げたサークルであり、「てつ子の部屋」とは、「ミアイ」の取り組みや、学生の姿勢を地域の方と接するなかで知ってもらおうという趣旨ではじめられた。今回で3度目の開催となる。
ミアイのHP(http://miaichan.web.fc2.com/)
地元の方のご好意で寄贈いただいたジオラマ(鉄道模型)を店の看板とし、ジオラマの走行を鑑賞しながら、お茶やお菓子を頂ける鉄道カフェの形をとっている。
横1m縦4mのジオラマは店の中央に設置され、その存在感は実に堂々としたものであった。

しかし、このカフェの目玉はこのジオラマだけではない。
「ミアイ」のメンバーが、あおぞら財団、地元の学童保育所に協力を求め、4人の小学生と1人の中学生にカフェの店員として手伝ってもらったのだ。



当日、あおぞらビルに集合した子どもたちは、おそらく、大学生と共に何かをすることも、カフェの店員の仕事をすることも始めてのことだろう。
緊張のせいか最初は大学生と何を話せばいいのか戸惑っている様子だった。
しかし、さすが小学生。場慣れしている大学生の力もあってか、わずか1時間ほどで皆仲良しになってしまった。

午後1時、いよいよ開店だ。
雨雲に覆われる天気のせいか、数十分たってもお客さんが訪れない。困惑気味の大学生。しかし、手伝ってくれている小学生の為にもここで立ち止まっていても仕方ない。
チラシを片手に、緑陰道路や住宅地を歩く方に声をかけ、趣旨を説明してまわる大学生。それに習って、子どもたちも笑顔で呼びかけを行ってくれた。

そのかいあってか、徐々にお客さんの数も増え、ウェイターの仕事を手伝ってくれる子どもたちも大忙しだ。「いらっしゃいませ。」「ご注文はお決まりですか。」など、練習では恥ずかしがってなかなか口にできなかった言葉も、お客さんを前にすると自然に口から出る様子だった。小さな店員さんに接客してもらうお客さんもつい笑顔がこぼれてしまう。



1階では、大学生手作りの射的や輪投げなどで小さな子どもにも楽しんでもらえた。空気砲を使った紙相撲、割り箸を使ったゴム鉄砲など細かな工夫が子どもたちの心をつかんだようだ。1階で楽しんでくれた子どもにはかき氷のプレゼントがあり、そちらが心をつかんだのかもしれない。



午後4時半、わずか3時間ほどのカフェだったが、大学生も小学生もお客さんも、皆笑顔で終えることができた。準備不足で冷や冷やする場面もあったが、皆の笑顔を見る限り、今回の「てつ子の部屋」は大成功だったようだ。


入場者数はおよそ30名!
ご協力頂いたみなさま、本当にありがとうございました。
大阪経済大学
緑のまちづくりサークル「ミアイ」
森井 隆二
エコミューズにご寄付と激励メッセージをいただきました
エコミューズでは、活動資金として、寄付金のご協力「ハモン基金」をお願いしています。
ハモン基金についてはこちら→http://www.aozora.or.jp/kifu.htm
先日、ある方からご寄付とともに、『資料館だより』最新号(第25号)に、こんなメッセージをいただきました。
「『もりもとまきのアーキビストの目』、感動しました。患者さんたちの往年の姿が目に浮かんできます。すごい戦いでした。」
「もりもとまきのアーキビストの目」は、『資料館だより』に連載中の、所蔵資料紹介コーナーです。
最新号(第25号)はこちら→https://www.aozora.or.jp/pdf/dayori25.pdf
エコミューズを、多くの方が見守り、支えて下さっていることを改めて実感し、感謝の気持ちでいっぱいです。『資料館だより』へのご感想やメッセージは、誌面づくりの大きな励みにもなります。これからも、さまざまな記録に向き合い、たくさんの大切なことを、たくさんの人に伝えていけるよう、がんばります。本当にありがとうございました。
写真は、『資料館だより』に執筆しています資料整理スタッフの森本と田尻、そしてハモン基金のご案内です。
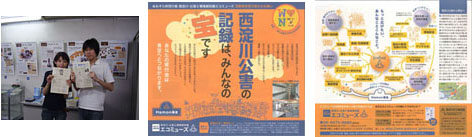
(もりもとまき・エコミューズ資料整理スタッフ)







