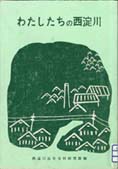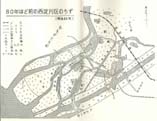━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
岡山初開催!
市民活動のための「環境アセスメント講座」 〜アセスメント制度と市民の役割を考える〜
2009年2月14日(土)、15日(日)、21日(土)、22日(日)
■チラシ(PDF版)
http://www.erca.go.jp/jfge/col/pdf/assh20_o.pdf━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
環境アセスメント制度とは、道路建設や発電所など大規模開発事業による
環境への影響を事前に調査、予測、評価をするとともに、市民とのコミュニケーションを
通じ、環境保全の観点からよりよい事業計画をつくり上げようとするしくみです。
この講座では、次の6点を大切にしています。
①制度のそもそも、市民の役割がわかる
②アセスの「いま」がわかる
③アセスの「実際」から学ぶ
④アセスの「現場」に立つ
⑤アセスを「体験」するワークショップ
⑥市民団体、NGO・NPO、参加者が元気になる
アセス制度が生まれて10年。市民の制度への理解と参加を広げるための連続講座です。
皆様ぜひご参加下さい。
■スケジュールとプログラム
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
2月14日(土)開催 【会場】ピュアリティまきび2階会議室
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
講義① 環境アセスメントと市民の役割
【時間】13:00〜15:00
【講師】浅野 直人 氏 (福岡大学法学部教授)
【報告】岡山県生活環境部環境政策課
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
講義② 風力発電所計画とアセス
【時間】15:10〜16:40
【講師】馬場 健司 氏 (財団法人電力中央研究所社会経済研究所主任研究員)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
2月15日(日)開催 【会場】岡山国際交流センター研修室
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ワークショップ 市民意見の形成
【時間】13:00〜16:30
【講師】傘木 宏夫 氏 (NPO地域づくり工房代表理事)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
2月21日(土)開催 【集合・解散】林原モータープール
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
現地見学 海から見学アセスの現場
【時間】集合13:00〜解散17:00
【案内】みずしま財団
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
2月22日(日)開催 【会場】岡山国際交流センター会議室(1)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
講義③ 廃棄物処理場とアセス
【時間】13:00〜14:30
【講師】田中 勝 氏 (岡山大学大学院教授、株式会社廃棄物工学研究所代表)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
講義④ 都市再開発とアセス
【時間】14:40〜16:20
【講師】梶谷 修 氏 (株式会社ポリテック・エイディディ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■受講料 1000円(全回通して)
■定員 30人(定員になり次第、締切)
■対象 NPO・NGO関係者、一般市民、学生、行政、企業関係者など
■問合せ・申込方法
環瀬戸内海会議 (松本 宣嵩 宛て)
TEL:090-3638-0187 FAX:086-243-2927
〒700-0973 岡山市下中野318−114
Eメール: webmaster@aozora.or.jp
次の事項を、ご連絡下さい。
(個人に関する情報は、本講座開催の目的以外には使用いたしません。)
〈1〉氏名(ふりがな)
〈2〉住所 〒
〈3〉電話
〈4〉所属(職場、学校名等)
〈5〉参加する日程(原則全回参加。全日参加できる方を優先。)
*【 】に○印をつけてください。
・2/14土 講座①【 】、講座②【 】
・2/15日 ワークショップ【 】
・2/21土 現地見学
・2/22日 講座③【 】、講座④【 】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■主催
独立行政法人 環境再生保全機構 地球環境基金
http://www.erca.go.jp/jfge/
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
■協力
みずしま財団 (財団法人 水島地域環境再生財団)
http://www.mizushima-f.or.jp/
環瀬戸内海会議
あおぞら財団 (財団法人 公害地域再生センター)
http://www.aozora.or.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━