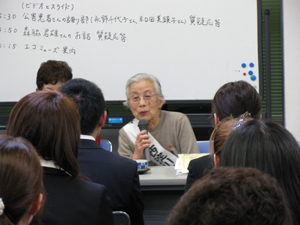2010年4月1日(木)に
財団法人淀川勤労者厚生協会(淀協)の
新入職員研修の受入を行いました。
淀協とは、西淀川に密着した医療機関・施設のネットワークで、
安心して住み続けられるまちづくりをすすめられている団体です。
まず、財団職員の眞鍋麻衣子より西淀川公害についての説明と
あおぞら財団の紹介を行った後、公害患者さんの語り部である、
永野 千代子さんと和田 美頭子さんのお話を聞きました。

永野さんからは、家族がぜんそくになり裁判に参加する経緯や
ご自身も公害病に認定されたお話がありました。

話の締めくくりに「私たちはもう歳もとったし、やりたくても
できない。若い人たちが西淀川の空気をきれいにしてほしい」と
熱いメッセージをおくられました。
続いてお話をされた和田さんは、公害病から裁判にかけての
心情の変化を語られました。
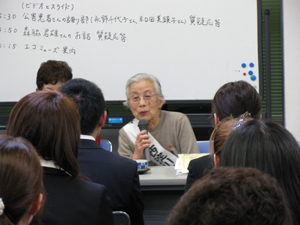
公害病がひどくなるにつれて
「こんなことで死にたくない」と思っていたのが、
病気のしんどさ、つらさから
「こんなことで生きてられない。死にたい」
となげやりになっていったそうです。
しかし、裁判の運動に関わるうちに
「こんなことで死んでたまるか!」と
思うようになっていったそうです。
お二人のお話に対する質疑応答では、
「西淀川を離れようと思わなかったのか」との質問に
「ほかに行っても看てくれる医者はいない。ここでの治療が1番。
そして西淀川の空気をきれいにしたい」と答えれました。
次にあおぞら財団名誉理事長で、西淀川公害患者と家族の会会長である
森脇 君雄さんがお話をされました。

森脇さんは淀協の職員として病院建設に関わった経緯や西淀川の現状に
ついてお話されました。
約束として孫・子のためにきれいな空気を取り戻すことを熱く語られました。
公害と戦ってきた三人のお話は、公害が過去のものではなく今も続いていると
改めて感じました。そしてきれいな空気を取り戻していく意義を再認識しました。
(北中)