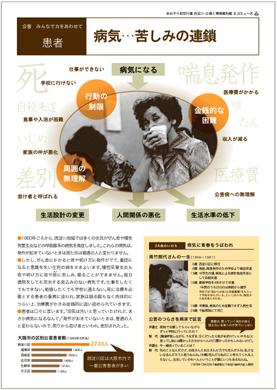エコミューズの悩み・・・それは
見てわかる西淀川公害の展示がないこと。
そのため、訪れた人への情報提供が不十分になることがしばしばありました。
見てわかる西淀川公害のパネルがあれば、
現在以上にわかりやすい情報を提供できるのに、と思い
常設展示パネルを作製することになりました。

■公害解決に尽力した人が登場する展示
そこでできたのが
西淀川公害の展示パネル
「公害・みんなで力をあわせて—大阪・西淀川地域の記録と証言—」
です、
おひろめ会が2008年12月12日に開催され、
パネルに登場した「人」たちも参加して公害への思いを語り合いました。

この展示パネルは、様々な立場の人の活躍を紹介しています。
あおぞら財団ではこれまで公害学習の教材を作成してきましたが、
現場の教師から
「公害の時、行政や医者、企業等いろんな立場の人がどのように努力をして公害を克服したのかがわかり、それを見て生き様を学ぶ職業教育になるようなものがほしい。」
との声があがっていました。
振り返ってみると、
これまでは患者の声を拾うことに精一杯で、
患者以外の方々の奮闘にスポットを当てることが
不十分であることに気がつかされました。
「みんなで力を合わせて」公害を解決してきたことがわかる、
いろいろな人が登場するパネルを作製しようということになりました。
作製中、登場する人々に意見を聞くたびに、
あれもこれも加えてほしいと色々な意見をもらいました。
公害解決のために携わった人々の思いの強さは半端ではなく、
情報量がどんどん多くなります。
しかし、伝えやすくするためにはコンパクトにまとめなければなりません。
板ばさみ状態になり、頭を抱える日々でした。
熱い議論の結果、
患者・医者・教師・国と自治体・ジャーナリスト・地元企業・弁護士・学者と、
様々な立場の人の活躍を描く展示パネルとなりました。
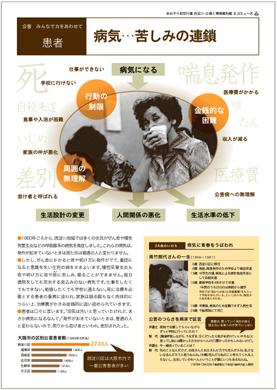
来館者の感想には
「とても分かりやすくまとめてあると思います。イラストや図が工夫してあってよかったです。」
「きれいな部屋になって、パネルも見やすくて、勉強になります!」
とあり、ほっと胸をなでおろしています。
■展示作製のために基金を募集
展示作製のために先立つものはお金ですが、
2007年度に募金を行って、
西淀川公害訴訟の被告企業、弁護士、市民、学者、
色々な立場の人たちから基金へのご協力をいただき、
半年で50万円が集まりました。
その資金を元手にして、
展示のデザイン・印刷と資料室のリフォームを行ったのです。
展示に登場する人たちだけではなく、
これらの作業を行った人々、
基金に協力した人々の思いも詰まった展示パネルになったといえると思います。
■貸出、中国語訳で広がる?
日本国内の様々な場所で展示してもらえるようにと、
貸出用を作製しました(貸出は2009年4月から)。
また、中国に日本の公害経験を伝えるための
中国語訳にも取りかかっています。
公害解決に携わった人々の熱い思いが、
この展示パネルを通じて広がっていくことを願っています。
開館日であればいつでも閲覧できるので、エコミューズにぜひおこしください。
(フルカラーB2版、13枚)
(あおぞら財団:林 美帆)